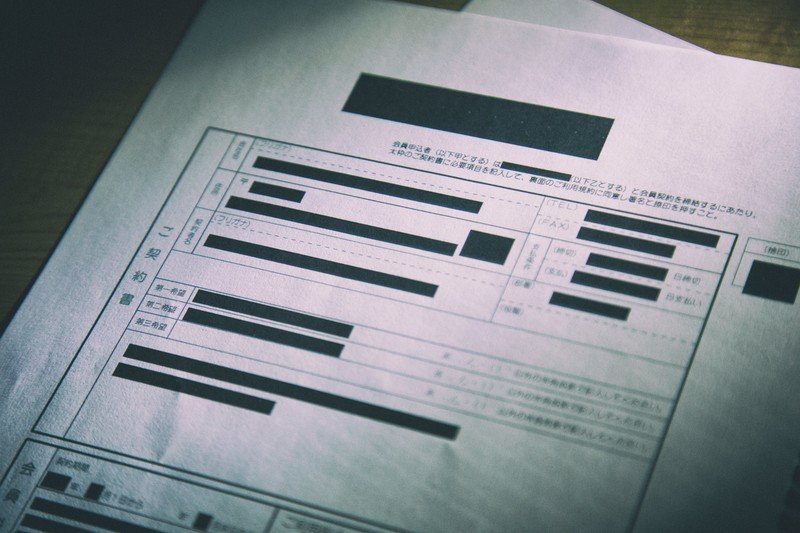ホーリンラブブックスのリニューアルした時の話
2025.03.17 00:00 (3ヶ月前) 投稿者:

弊社が運営しているECショップにBL専門サイトのホーリンラブブックスがあります。

弊社が運営しているECショップにBL専門サイトのホーリンラブブックスがあります。


もう気がつけば9月も終わる!気づけばハロウィン、クリスマス、そして新年の足音が聞こえます。新年開けると誕生日と苦悩が私には待ち受けていますが皆様いかがお過ごしでしょうか?


これまで弊社ではさまざまなスマートロックを活用してきました。


ども、お久しぶりです。 オンプレのインフラ構築を担当することが多い四斗邊です。 今回は社内の要望でmysql8.0サーバーを社内ネットワーク上に構築する!というのが目標です。 結構ありふれたネタだと思いますが、社内に向けた手順書のような形で残しておきたかったので今回記事しました。


株式会社TORICO情報システム部の四斗邊です。 PMS、ISMS関連の後編です。 今回はPマーク認証、ISO27001認証を取得する際のコンサルを選ぶポイントについて話したいと思います。

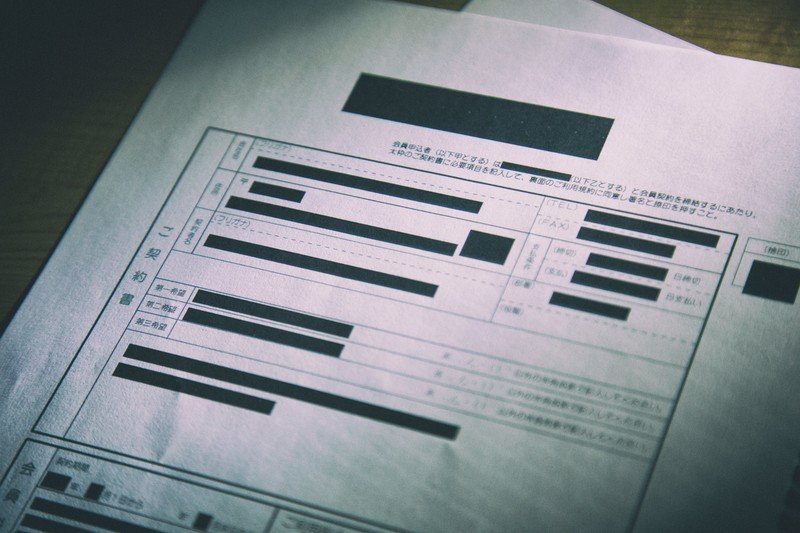
はじめまして株式会社TORICO情報システム部の四斗邊です。 いきなりですが、PMSとISMSについてお話したいと思います。 なぜこの話をしようと思ったかといいますと、株式会社TORICOでは、2021年1月にPマーク認証を取得、2021年2月にISMS認証(別名ISO/IEC 27001)を取得したからです!